ばけ猫オパリナ あるいは九度転生した猫の物語
ペギー・ベーコン 宮本神酒男訳
光と影
フィンリー家の子どもたち、フィルとエレン、ジェブは一番年下のジェブが5つになるまで町に暮らしていました。両親が荒れ野原村の近くに家を買い、一家で田舎に引っ越すことになったのは、八月の終わりのことです。
その家は大きいというよりだだっ広く、とても古い屋敷でした。柔らかくて厚みがある、緑色のふさふさした毛なみの芝生の上に舞い降りたかのようにそれはたっていました。古くて大きな木々が立ち、その下にはきまって苔(こけ)のかたまりが生えていました。また古い家畜小屋があり、ちいさな小屋だらけの古い庭がいくつもありました。そこには水仙の池があり、流行遅れの花々が咲き、茂みに囲まれていました。向こうには牧場や牧草地がつづき、岩があり、泉があり、小川が流れていました。いうまでもないことですが、それらはみなとても古くて、ずっと昔からあるものでした。でもフィンリー家の子どもたちにとってはなにもかもがあたらしかったのです。
お母さんとお父さんが家の整理整頓に追われているころ、子どもたちは外に出てあたりの自然を探索しました。あちこち柵ばかりで「芝生に入るべからず」と書かれた標識が貼られた町の公園とはたいへんなちがいです。野原や森には見るべきものがたくさんあったので、子どもたちは親がなにをしているか気にもとめませんでした。
ある朝、雨が激しく降っていました。朝食を終えるとお母さんはお父さんにいいました。
「今日がその日だわ。きっとそうだわ」
「たしかにそうだな」とお父さんは楽しそうにうなずくと、子どもたちにいいました。「おまえたち、こっちにおいで。サプライズがあるんだ」
お父さんのあとをついて子どもたちは階段をあがり、それから廊下を進むと扉がありました。扉をあけて部屋のなかに入ると、そこには子どもたちが見たことのない光景があったのです。
「ここはおまえたちのお城だ」とお父さんは宣言しました。
広々とした羽目板張りの部屋には暖炉がありました。家具は一式そろい、ゲームや本がたくさん置かれていました。箱があり、ジェブのぬいぐるみや積み木がめいっぱい入っていました。窓の横に製図台が、もうひとつの窓の横に大工の作業台があり、大工道具もそろっていました。
「そのイスを見てごらん」とお母さんは、使い古された赤いビロード張りの肘掛けイスを、喜びに満ちた子どもたちにさし示しました。「私たちはこの部屋でこのイスを見つけたの。とても古いイスで、下の居間に置くにはくたびれすぎているわ。だからあなたたちにここで使ってほしいの」
「この部屋は明かりがないからな」とお父さんはいいました。「でもオイル・ランプをおまえたちに与えるのは危険だ。日中は光がさしこんでくるから問題ないのだが」
お母さんとお父さんは神への感謝の言葉を唱えると、子どもたちを部屋に残したまま階下におりていきました。町に住んでいたときは、子どもたちは寝室で遊ぶしかありませんでした。家族の居間では、オモチャ遊びがいっさい許されていなかったのです。子どもたち自身の部屋ができたので、オモチャ遊びも自由にできるようになりました。
何日間も外は土砂降りの雨が降りつづきました。でも子どもたちは遊び部屋で過ごすことができたのでかえってうれしかったのです。学校で大工の勉強をしていたフィルは本棚を作りはじめました。エレンは引っ越しの日のことを絵に描いています。ジェブはブロックで汽車やトンネルを作りました。それは床という床、家具の間や下を縫うように無限に走り続けました。
はじめ天気が悪いからといってだれも問題にしませんでした。けれども三日目の午後遅く、エレンは物憂げな顔をするようになったのです。フィルはおなじことをつぶやくようになりました。
「雨、やまないかなあ!」
ジェブは汽車を投げ捨て、塔を崩し、廃墟のなかにすわって、しずかに、もの思わしげに古い赤いイスのほうを眺めました。
しまいにフィルは道具のすべてをわきに押しやって窓越しに黒いずぶ濡れの木々のほうを見ました。
「前よりどんどん強く降ってきているし、あたりはどんどん暗くなってきている。雨、とまってくれないかなあ」
「もうわたし、これ以上描けないわ」エレンは絵具箱を閉じました。「ジェブ、あんたも積み木を箱に戻しなさいよ」
幼い弟は答える気にならなくて、黙っていました。
「ジェブ、聞いてるの?」エレンはいっそう厳しくぴしゃりと言いました。
「ジェブ、いわれたことは、すぐやるんだ!」フィルは命令口調でいいました。「ベッドに早く入んないと、おばけが出るぞ」
もっと大きな子どもなら、このおどしは「おいた」をしているジェブにきき目があったかもしれません。しかし今回はちがったのです。
「ジェブ、どうしたんだ」フィルはジェブをにらめつけました。
「ぼく、子猫を見ているんだ」
みなおどろきました。
「なんだって?」
「白くてきれいな子猫がいるんだ」
「ここに猫がいるわけないだろ! ばかなことをいうな」
「きっとあれよ」エレンは声をはりあげて、あいだに入りました。「スカーフか何かだと思うけど」エレンのことばはしりすぼみに消えました。
部屋のなかはまっくらでした。しかし古い赤いイスのあたりから輝くものがあらわれてきたのです。それは時計の文字盤が光っているようでもありました。しだいにそれが猫のかたちをしていることがわかってきました。しっぽだけ立てて、ぐっすり眠っているようです。子どもたちは猫の幻影をじっと見ました。それは脚を伸ばし、頭を上げると、あくびをし、両目をあけました。
年長のフィルとエレンは息をのみ、驚きのあまりへたりこみました。
「なんて目だろう! 素敵な目だ! ミルク色の輝きにバラ色とコバルト色、そして緑と紫のきらめきがまじったようなオパールの目!」
「とてもきれいな猫」ジェブはかん高い声をあげました。「夢みたい!」
「よくいってくれた、若者たちよ」とささやくような落ち着いたささやき声が聞こえてきました。
夢がしゃべった!
遊び部屋で音がしたわけではなさそうです。カーペットの上の子どもたちはうっとりとひじ掛けイスの上の幻影を見ました。
猫の幻影は輝く前脚で輝く顔をきれいにふきはじめました。そのふさふさした毛並みはイソギンチャクのように揺れ、きゃしゃな口から小さな青いピンクの炎のような舌がしきりに出入りしてそれをなめています。幻影はとてもあかるく輝いていたので、ロウソクほどのあかるさがありました。猫はそのうち頭を下げ、また両目を閉じました。
「また寝ちゃうの?」フィルはお願いするようにいいました。
幻影の猫は片目をあけると、虹のすべての色を含んだ光を顔からはなちました。
「よく知っているだろうが、若い人よ」とやわらかい声でいいました。「あたしはいつでも寝たいときに寝る。それだけの話だ」
「でも話をしたいと思いません? いくつかききたいことがあるんだけど」
「調べたいことがあるなら百科事典をみなさい」
「あなたのことを知りたいわ」エレンは必死できこうとしました。
「まあ、たぶん話さないな。人を避けているからね。人に知られないようにしているのだ。自分のことは秘密の存在にしてきた。経験からわかったことだが、あたしがここにいることはだれも知られんほうがいい」
「これはいわないといけないけど」とフィルはいいました。「ぼくたちが知っていることは気にしてないの?」
「まわりに触れ回るのなら話はべつだが、あたしをほうっておいてくれるなら気にすることもないだろう」
「でもあなたがどなたかということだけ教えてもらえませんか」
「だれかだって?」煙のようなものをモクモク出しながら、幻影の猫は王者のような貫禄を見せて居住まいを正しました。
「わがはいは偉大なるあたしである。大気のもっとも等級の高い上質のものから作られた別世界からやってきたきよらかな存在である。光にみちた精霊である」
「じゃあなんてあなたのことを呼べばいいのかしら」とエレンはおずおずとたずねました。
「呼びたかったら呼びなさい、お嬢さん!」と精霊はしゃがれた声でいいました。「あたしはVIPだ。ベーリーイ、インポータントォ、パアソンだ。呼ばれたって行かないけどね。ぜったい行かないけどね!」
「妹はそういう意味でいったんじゃないです。あなたのお名前をうかがっているのです」
「おお、そういうことなら、おしえてせんじよう。わが名はオパリナ。あたしはたくさん称号をもっておるぞ。まったきかしこき者。はなばなしくしっぽを振る者。文化ありし真珠。比類なき貴婦人。ペルシャの王妃……」
「王妃ですって?」エレンは興奮しました。「ほんものの王妃!」
「ほんものなんてないさ」オパリナは鼻であしらうようにいいました。「ほんものなんて世の中にはかけらもない! その考えを滅せよ! あたしは精巧なにせもの!」
「でもあなたはじっさいここにいる」フィルの頭は混乱していました。
「そう、ここにいる。あんたが望めばね。このちっぽけな部屋にだけ」
「あなたはどこから来たの?」フィルとエレンは同時にききました。
「どこかから来たんじゃない。あたしはいつもここにいるのだ」
「ここ?」
「そう、ここ」
「あなたを見るのははじめてなんだけど」
「それは暗さがたりなかったからだ。この二日間、あんたたちは夕暮れになると下におりていった。今日はおりなかった。それだけのことだ」
「どれくらいあなたはここにいるの?」
「ハロウィーンのころには二百年になるかな」
「二百年だって!」フィルは叫びました。
「それは年をとりすぎだわ。猫はそんなに年とらないわ」エレンはそうつぶやきました。
「あなたは二百年もここで何をしていたんですか」とフィルがたずねました。
「あたしはここにとりついているのだ」
「それってどういうことですか」とエレン。
「だからいまいったように、あたしはこの部屋にとりついているのだ」
「なんてことだ!」フィルはため息をはきました。「つまりあなたは幽霊ってこと?」
「まあそういうことだ。影、精霊、おばけ、幻、幽霊、どれもおなじこと。だからあたしのことはしゃべらないほうがいいって忠告しておく」
「オパリナって、ぼく、ちゅき」とジェブはありのままの気持ちをいいました。
「ジェブにしゃべるなって無理な注文ね」とエレンはため息まじりにいいました。
「注文はいらんよ」と口をはさんだのはオパリナでした。「しゃべりたきゃ、しゃべればいい」
おばけの猫は渦巻星雲のようにくるくるまわりながら、ひじ掛けイスのくぼみに入って落ち着きました。猫はあくびをしながらいいました。
「質問が多すぎてあたしゃつかれたよ。猫寝の時間だしね」
猫は目をつむり、鼻をふさふさしたしっぽの毛のなかに埋めました。そしてもやのなかですやすや眠っています。
「あんたたーち!」階下からお母さんの声がひびきわたりました。「おりてきて手と顔を洗いなさい! もうごはんの時間よ!」
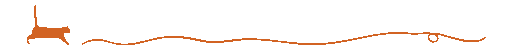
つぎの日、フィルとエレンはおばけに会ったのにどうしてこわさを感じなかったのだろうかと不思議に思いました。
「オパリナがこわいって、ちっとも思わなかったわ」とエレンはいいました。「オパリナが目をあけたとき、おどろいてとびあがったけど」
「いちばんきれいな大気の成分からじぶんはできているって、オパリナはいってたよね」とフィル。「なんだかぞっとしたけど、こわくなかったのはそのせいかな」
「ジェブもこわがってなかったわ。おばけごっこをしたときはあんなにこわがってたのにね」
フィルはうなずきました。「どうしてかな。おばけの正体がぼくたちだってジェフは見破ってたよね」
「おばけのふりしておどかしたら、いやがっていたのはたしかね」とエレン。「もうあんなことやめましょう」
「いややるべきだよ」フィルはきっぱりといいました。「勇敢であることとはなにか、教えなきゃ」
「ジェブはすでに勇敢よ。オパリナをはじめて見たとき、泣かなかったわ」
それはとても美しい朝でした。この絶妙に美しい時間、遊び部屋は目もくらむほどの光で満たされました。子どもたちはおばけがもう一度やってこないかと待ちわびていましたが、日中、オパリナの姿は見えずじまいでした。
「夕ご飯が終わるまで遊び部屋は暗くならないようだ」とフィルはものうげな顔でいいました。
歩けば歩くほど広がっていく砂漠みたいに、終わるのを待てば待つほど昼間はのびていきました。フィルとエレンはいい天気もうらめしく思いました。悪天候のほうが暗いぶんよかったのです。
「オパリナならこの家で起こったことすべてを知ってるはずだ」とフィルはいいました。「この家が建てられたときからのすべてをね」
「もしそうなら」エレンは疑わしそうな顔でいいました。「オパリナはわたしたちの質問にうんざりしていたはずだわ。ジェブはなにもきかなかったから、オパリナはジェブが好きなのよ」
「ジェブはオパリナがきれいだといっただけだ」とフィル。「オパリナはしゃべってくれると思うよ。閣下とよんで、それなりに敬意をはらえばね」
夕陽が沈むのにも、永遠のような長い時間がかかったかのようでした。夕陽が沈んだあとも金魚の群れのような光る雲が残っていました。そのためしばらくのあいだ、遊び部屋は昼間のように明るかったのです。
ようやく明かりがうすまってきたので、子どもたちは赤いいすの前の敷物の上に膝をついて待ちました。
「オパリナがあらわれた」フィルはささやきました。
たしかにいすの上に霧のようなものがあらわれ、それは渦を巻きはじめ、ばらばらになり、またまるくなり、しだいに眠っている灰色かがった猫の形になっていきました。
「起こさないほうがいいみたいね」エレナはふりむいてささやきました。「起こされるの、好きじゃないみたいだから」
でも突然ジェブが興奮して叫んだのです。
「オパリナ、世界一かわいい!」このジェブの声でオパリナは目を覚ましました。
オパリナの姿はますます輝いています。ジェブはききました。
「オパリナ、ネズミつかまえられるの?」
「しっ、ジェブ!」エレナはジェブをにらみつけました。「質問はわたしたちがするから。ばかげた質問をオパリナはとりあってくれないわ」
「それは当を得た質問というものです」おばけ猫はいいました。「こたえは否(いな)です。近頃、ネズミをつかまえるなんて、はしたないことはいたしていません。ただネズミを追っ払うだけなのです。あたしの姿を見ただけでネズミどもは右往左往するのですから」
オパリナはほほえみました。「でもむかしはよくネズミをとっていたものです。とくに九つの生まれ変わりの最初のとき、あたしはネズミとりが得意だったのです」
「九つの生まれ変わりですって!」エレナはおどろきの声をあげました。「あなたは九回も生きたっていうのね」
「正確には一回のほんとうの生と八回のほんとうでない生ですけどね」
「ほんとうの生って」とフィル。「ばけ猫になる前の話だね」
「そういうこと!」
「ぜひ話してほしいな」エレナはことばを選びなおしました。「閣下、ひざまずいてお願いいたします!」
フィルもひざまずいて、かさねていいました。「閣下どの、寛容な心で、あなたの人生のことをお教えください。そうしていただけるなら、わたくしどもはよろこんであなたさまの永遠の奴隷となるでしょう」
オパリナはゴロゴロとのどを鳴らしています。
「あたしはおまえたちが話すのを聞くのが好きである。おまえたちの忠誠心はむくわれることだろう。それほどに話を聞きたいのなら、ひとつやふたつ、話をきかせてあげないでもない」
⇒ つぎ