ミケロの旅日記
7月20日 ミャンマーの村(2)
暖かく迎えられたことは本当にうれしかったけれど、われわれがここに来た目的は呪術師を探し出すことだった。そのためにはもうすこし奥へ入る必要があるだろう。ラワン族の中心都市プータオやカチン州の州都ミッチーナにまで行くことは許されないが、もうすこし先まで進むのなら差支えないだろう。(国境付近の行き来は地元民ならほとんどの場合可能である)
 ンマイカ川(独竜江)に架かる長い吊り橋。
ンマイカ川(独竜江)に架かる長い吊り橋。
最初の集落を抜けると大きな吊り橋があった。ンマイカ川は独竜江よりはるかに広くなっていて、それに架かる吊り橋もそれに応じて長くなっていた。竹でしっかり編まれているため危険は感じなかったが、雨脚はいっそう強くなり、それにつれて風が出てきたため、橋の中央部では橋全体がたわんでいるように思われるほど揺れた。
橋を渡ったところから上の道に出るまでは、まるで険しい山を登っているかのようだった。それでなくとも急斜面なのに、雨に濡れて岩場が滑りやすかった。平坦な道をしばらく行くと、小さな花畑があり、その向こうに高床式の家屋があった。
階下の犬に吠え立てられながら階段を上がり、散らばった靴の上にからだをのばして中をのぞいた。囲炉裏を囲む数人のなかに、Nさんの知っている顔が認識されたようだ。彼女の親戚のうちだった。


この家の主人は鼻筋が通り、「俳優をやればいいのに」とつい思ってしまうほどのイケメンだった。独竜江下流からミャンマー側にかけての人々にはこういう顔立ちが多いのだ。彼ら(ラワン族)はわれわれのもつミャンマー人のイメージとは異なっていた。
囲炉裏を中心とした生活は中国の少数民族とよく似ていた。ただし入口からすぐの囲炉裏の部屋は客間兼居間であり、奥には家族専用の囲炉裏部屋があるのだった。雲南や四川の奥地の囲炉裏部屋よりはずっとモダンな作りだった。ミャンマーの地図を見ると、このあたりは北辺の隅になるのだが、そのわりには未開の地という印象は受けなかった。
われわれは軽食を取りながらプータオで作られたらしいラワン族のアーチストによる音楽ビデオの(DVDではなく)VCDをいくつか鑑賞した。驚くべきことにそれらの曲はかなりのレベルにあり、映像もまずまずの出来だった。プータオの町で若い男女がむつみあうシーンは都会のカップルそのものだった。
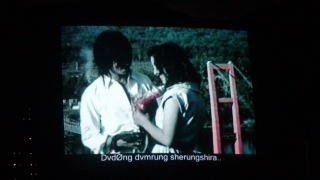

「漢族みたいだな」とガイド役のX氏は溜息まじりに言った。
これはどういうことかというと、雲南の片田舎にいると、北京や上海の文化(漢族の文化)は先進的でまぶしく見える。このビデオのなかのラワン族も中国側のラワン族(独竜族)から見ると先進的でまぶしいのだ。中国からミャンマーを見るとき、上から目線になりがちだが、その驕った考えはみごとに粉砕されてしまったのだ。「ラワン族=未開の民族」というのは偏見にすぎなかったのだ。


呪術師に関しても同様のことがいえた。
「ナムサ(呪術師、シャーマン)についてうかがいたいのですが」
「ナムサ? ナムサなんていないよ」
「じゃあドゥムサ(カチン族のシャーマン)はどうですか?」
「われわれはクリスチャンなので、そういうのは死に絶えたんだよ」
主人は困惑した表情を浮かべた。
私はあとでNさんにたずねた。
「いったいどういうことなのだろう。叔父さんは呪術師に殺されたのではないのですか」
「たぶんナムサではない、ということね。シャーマンはいなくなっても、呪術は残っているはずだわ。現にわたしの叔父さんは殺されたのだから」
おそらく現代から落伍しているように見える文化は隠したがる傾向があるのだろう。その存在を認めたところで、呪術をおこなっている人のもとへ案内するということはありえない。作戦を練り直さなければならない。
中国、とくに雲南にはまだ各所に憑き物の風習が残っている。たとえばある家には猫の憑き物があるとされる。そうするとこの家の者は魔術的な力をもっているとして恐れられるいっぽう、差別を受けてしまうのだ。濾沽(ルグ)湖のモソ族にもそういう風習が残っていた。ある憑き物の家の娘は、美人であるにもかかわらず、結婚することができなかった。この風習は日本にも残っている。犬神はその一例である。貢山のリス族の女性も憑き物のために恐れられていたのだ。
ラワン族もキリスト教化されているにもかかわらず、憑き物の風習を根絶することはできなかった。触れてはいけない文化の側面だったのだ。私はこれ以上の追及はやめることにした。触らぬ神に祟りなし、ということわざがいうように、深く追及すると、憑き物の神に祟られてしまうだろう。つぎの機会にミャンマーのラワン族の研究者とともにこの地域に入りなおそうと私は決意した。

この家からの帰り、最初の集落のなかの家を訪ねた。この家の人々もNさんの親戚筋にあたるらしく、暖かく迎えてくれた。ミャンマー人というより中央アジアの人にみえる主人は、大きな子供が三人いるという。長男はなんと今朝方私をどやしつけた背の高い青年だった。その話をすると家族は大笑いしていた。私をとがめる権威などこれっぽっちもなかったようだ。