老いについて 宮本神酒男
痴呆症哲学者カント
「紳士のみなさま、私はかよわい老いぼれです。私のことを子供と思ってくださってもかまいません」
J・H・W・スタッケンバーグの『イマヌエル・カントの生涯』(1882)によると、1799年頃、つまり75歳になった頃、哲学者イマヌエル・カント(1724−1804)は自宅の客を前にして、何度もこう言うようになったという。カントといえばいわずと知れた『純粋理性批判』や『実践理性批判』などを著したドイツ観念論哲学の祖とされる大哲学者である。その人類の叡智の最高峰というべき人間から、このような自嘲気味の言葉が発せられたのである。しかしこの頃はまだましだった。
カントは睡眠をもっと取るべきだと感じながらも、しばらくはそれまでと同様、朝5時に起床していた。しかし夜、床に入る時間を数分間だけ早くした。それから就寝時間を夜9時にかえ、それから一挙に夕方5時に早めた。彼は散歩をする習慣を持っていたが、その距離、時間はみるみるうちに少なくなっていった。
そしてついに二人の婦人の手助けがなければ起床できないほど、体は弱くなっていた。この時期に彼は屋外の散歩をやめてしまった。室内でも、歩くことも立つこともできず、床の上に這いつくばることがあった。
ある夜、椅子に腰かけたままうとうとしていると、テーブルの上のランプの火が木綿のナイトキャップに燃え移り、あわや焼死しかねない事態になった。(このときは燃える帽子を床の上に払い落とし、踏んで火を消し、事なきを得た)
78歳になったカントは、急速に記憶能力を失ってしまう。その前年まで、体は弱っていたが、記憶力はそれほど低下していなかった。しかしこの時期、彼は一日に何度もおなじことを言うようになった。
彼はそれまでも、便箋や封筒の空いたところや、特記メモ用の紙の切れ端などに書き留める習慣を持っていた。しかしいま、彼は繰り返しを避けるための、あるいは普段の会話をスムーズにするための備忘ノートとして使うようになったのだ。これは現在も記憶障害者が用いる方法である。
こうした紙切れの類が山のようにたまって訳が分からなくなったため、ワシアンスキー(元はカントの学生で、研究者。のち牧師となる。後年再会し、カント邸をよく訪れていた)は専用の小さな備忘ノートを作製した。この備忘ノートの一冊(約1か月使われた)にカントは「わが理髪師の名はローガルである」と5度も書き記しているという。
彼はまたその日に起こったできごと、ゲストに呼びたい人の名、食事に出したい料理、友人との会話のなかで気になった自然科学に関することや旅行、政治、その他もろもろの似たようなことが備忘ノートに記された。
しかし書いたことをすぐ忘れるので、何度もおなじことを書いた。小さなどうでもいいことを繰り返し書き入れた。たとえば彼はこう書き記した。
「6月、7月、8月は夏の3か月」*6、7、8月はドイツ語でユーニ、ユーリ、アウグスト
これがあの「アプリオリな認識」の哲学者のメモだと思うと涙を禁じ得ない。それほどにも老化(この場合は老人性痴呆症。おそらくアルツハイマー症)のパワーはすさまじく、知の巨人をも平凡な痴呆老人に変えてしまうのである。
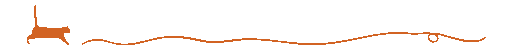
最近では『百年の孤独』などで知られる20世紀の文豪ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928−2014)や「刑事コロンボ」役で有名なピーター・フォーク(1927−2011)の家族が、彼らが痴呆症やアルツハイマー症であることを公表している。痴呆症が進行する女優南田洋子(1933−2009)を献身的に介護する夫長門裕之(1934−2011)の姿は、テレビの前の視聴者を感動させた。
しかしこうやって公表されるのはごくわずかにすぎず、大半の痴呆症患者は隠されたままひっそりとこの世を去っているのである。
逆に高齢でも活躍している人々がいる。映画監督新藤兼人(1912−2012)の奮闘は記憶に新しいが、その上を行くのがポルトガルのマノエル・ド・オリヴェイラ監督(1908−2015)である。彼は典型的な大器晩成の映画監督で、作品のほとんどは70歳を超えてから作られたものである。才能が遅れてゆっくりと開花したほうが、アーティストとしての寿命は不思議と長くなるのである。
*最近私はジョージ・R・R・マーティンの『氷と炎の歌』シリーズをオーディオ・ブックで聴きはじめたのだけれど、ナレーターは1923年生まれの(現在93歳)俳優ロイ・ドートリスである。ネットで調べると、どうやら吹き込んだのがもっとも新しいのはシリーズ4の『乱烏の饗宴』で、2011年後半らしい。朗読時間は33時間以上である(シリーズ5『竜との舞踏』は49時間)。88歳での長時間朗読(というより声の演技)には敬服するしかない。ドートリスは第二次大戦中の1942年から45年までドイツ軍の捕虜となり収容所に入れられていたという。演じた回数1782回はギネスにも認められているらしいが、この俳優ほど「超人」いや「超老人」という言葉がふさわしい人もいないだろう。
1922年生まれのおなじみの俳優クリストファー・リーも「超老人」に認定したい。最新作は『ホビット 決戦のゆくえ』(2014)である。(2015年6月7日永眠。冥福を祈ります)
作家では『パキスタン行きの列車』や『シーク教の歴史』『首都デリー』などで知られるインドのクシュワント・シン(1915−2014)に私は注目してきた。エスプリにあふれた自伝『真実、愛、そしてちょっぴりの悪意』を書いたとき、彼はすでに87歳だった。彼には少し下品なところがあり(そこが彼の魅力でもあるのだが)この自伝の前書きにも「この歳で朝立ちしたぞ」と無邪気に喜んでいる。
2012年には、デリーのロディ・ガーデンに集まる80代の老人たちがさまざまな話題、とくに好んで下ネタを取り上げる小説『サンセット・クラブ』を執筆した。95歳の作家の小説なんて、それだけで読むのが恐くなってしまいそうだが、意外にもなかなかの傑作なのである。この調子でいけば、100歳の現役作家も夢物語ではないと思われた。しかし残念ながら、100歳を目前にして永眠。茶目っ気たっぷりのクシュワントの表情が浮かんできそうである。
*2014年11月27日に亡くなった英国の推理作家P・D・ジェイムズ(1920−2014))のフィクション最後の作品『秘密』が出版されたのは彼女が88歳のときだった。評論集『推理小説について語る』が出たのはその翌年である。彼女自身がインタヴューに答えているのだが、ボドリアン図書館の依頼に応じて執筆したという。「読者として、作家として」50年以上も親しんできた推理小説に恩返しをしたかったのかもしれない。これらの作品は若い頃に書き溜めて置いたものではなく、新作ということになる。おそるべき老人である。
⇒ つぎ